![[ 海外出展 ] INSIGHT 08 伝統工芸の海外展開](https://biznavi.smrj.go.jp/wp-content/uploads/2018/03/insight08.jpg)
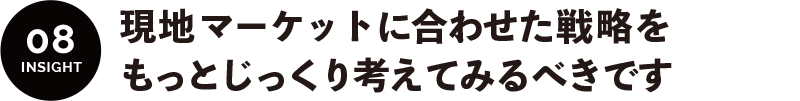
さまざまな海外展開プロジェクトの舵を取り、日本の伝統工芸を国内外へ広く紹介している堀田卓哉さん。ビジネス専門家の視点から、海外市場に向けたローカライズ(現地向けの仕様にすること)の重要性や新たな販路開拓の取り組みについて伺います。

目次
どうすれば海外で勝負できるか
そのやり方を伝えたい
僕は1977年生まれ、いわゆるロスジェネ世代です。中・高時代からあまり日本に良いニュースがなく、日本にいても自分の未来は明るいものにはならないのではという漠然とした思いがあって、つねに海外に出たいと思っていました。
でも、ヨーロッパ留学後、縁あって浅草に住みまして、有名な「三社祭」を見たんですね。これはすごいと驚き、祭に参加したい一心で地元の青年部に入りました。すると、提灯屋の六代目だとか、もなかの皮をつくり続けて160余年の老舗の跡取りといった同世代の若者がたくさんいたんです。彼らが「日本の文化をより良いものにして、次の世代に引き継いでいくことが仕事なんだ」と広い視野で自分の役割を考えていることに、すごく新鮮な驚きを覚えました。
同時に、彼らの悩みも見えてきたんです。自分の技で世界に出たいし、勝負できる自信もある、でも「どうやったらいいのか、わからない」と言うのです。だったら、そうした専門性を磨いてきた人たちと僕みたいなビジネスの専門家が組むことで、もっと日本を盛り上げるようなことができるんじゃないか。そう考えて会社を辞め、独立しました。

市場に合わせたローカライズが「売れる商品」をつくる手法
ところが僕、最初に大失敗をしたんですよ。伝統工芸の職人と新鋭デザイナーのコラボでミュージアムショップグッズをつくる「Tokyo Crafts & Design」に携わり、イタリアの「ミラノサローネ」に出展したのですが、なんと1個も売れなかったんです。
イタリアのバイヤーたちはみんな、「日本には素晴らしい技術があるんだね!」と褒めちぎってくれるのですが、じゃあ買うかというと買わない。「美しい。でも、ちょっとサイズが小さいな」とか、「芸術的だよ。でも、こっちでは売れにくい色かも」というように必ず「でもね」がついて、実商売につながらないんです。やはり国内のミュージアムショップを意識してつくった商品ですから、海外向けにはつくられていなかったということなんですね。海外で売りたいのなら、やはり市場に合わせてローカライズ(現地向けの仕様にすること)しなければならない。
その後、中小機構の「Next Market In」事業では、「ターゲット市場のバイヤーやデザイナーと一緒に、ローカライズした商品開発をする」という手法をとりました。3年間やらせていただいた結果、すべての企業が成功するわけではないですが、売れる確率が高い手法であることは間違いないと感じています。
その商品は、本当に海外のブランドと闘えるのか?
海外展開をするのであれば、「現地でどのようなポジショニングで売っていくのか」「どういうマーケティング手法でいくのか」といった戦略について、本気で考えていかないと勝ち目はありません。
たとえば、僕はいま江戸切子のプロジェクトに関わっていますが、どのようにヨーロッパ市場で売っていくかというアイデアを思いつくまでに1年かかりました。なぜなら、江戸切子は日本の伝統工芸ですが、じつは約130年前にイギリスから来日した技術者の指導で花開いた産業です。だから、「江戸切子です」とヨーロッパに持って行っても、向こうは「ああ、日本にもカットグラスがあるんだ」と感じるだけで、その瞬間にサン・ルイやバカラ、ボヘミアンガラスといった有名ブランドと競合する存在になってしまう。さらに関税がかかってバカラより高い値段になったら、「どうやって売ればよいのか」という話じゃないですか。
これと似たようなことが他の伝統工芸品や日本製品でも起こっています。「国際見本市に出たけど、全然買い手がつかなかった」という話をよく聞きますが、海外のお客様の視点に立ってみれば「それはそうだろう」ということなのです。
コンセプトが決まれば、マーケットもアプローチも決まる
悩んだ末に僕たちがどのように江戸切子をヨーロッパで売り出したかというと、「和食をもっとも美しく飾ることができる器」という切り口でした。「これだ!」と気づいたのは、堀口切子の堀口社長と話していたときです。
「昔の和食の料理人は、切子は和食をもっとも美しく飾ることができる器だと考えていたんだよね。だから堀口硝子(堀口切子の親会社)にはさまざまな切子の型が残っているんだよ」
それはすごい資源だと驚きながら、僕たちは「そうか、和食カットグラスというポジショニングでヨーロッパへ出れば、他のブランドとはまったく違う土俵で勝負ができる!」と考えました。であれば、マーケットは日本食料理店や日本酒を取り扱っているバーに絞られてくるので、BtoBの取引になってくる……というように、コンセプトが決まると自然にマーケットも決まってきます。マーケットが決まれば、そこにどうアプローチしていくかという戦略が立てやすくなります。
自分たちの思いを伝えることでファン(支援者)が増えていく
結果的に、僕らは展示会には出展せず、まったく違う手段で販路開拓を行いました。最初に仕掛けたのは、ロンドンの日本大使館で開催したイベントです。“和食カットグラス”へのニーズや興味関心を探るために和食職人と堀口切子のコラボレーションで開発した器の展示や対談イベントなどを行ったところ、連日来場者が詰めかけ、『Evening Standard』(ロンドンの夕刊紙)にも掲載されました。
ところが、勇んで営業活動を始めてみると、肝心の日本食レストランには売れなかったのです。向こうは丁寧に皿洗いをしないので、頻繁に皿が割れるらしく、とても1個2万円もする器は使えない。「欲しいけど買えない」と言うのです。
そこで再び発想を切り替え、ロンドン市内のギャラリーを借りて、約130年前に来日したイギリス人技術者の曾孫である硝子歴史研究家サリー・ヘイデン氏と堀口社長との対談イベントを行ったところ、知識層の方が100人以上も集まり、熱心に聞いてくださいました。こうして地道なファンづくりに努めた結果、個人で買ってくださるお客様が増え、初めて常設の小売店舗が決まり、レストランからも注文がくるようになってきたのです。
展示会でものの30秒ほど商品を見ただけで値段で却下されるという世界よりも、自分たちに興味を持ってくれる100人に2時間、自分たちのモノづくりに対する思いを伝えることのほうが重要なんじゃないかと思います。志に惹かれるのは、国境を越えて同じなんじゃないかな。僕たちだって、その会社のフィロソフィーやつくり手の思いに共鳴できて初めて、心からサポートしたいと思いますから。

富裕層のライフスタイルを知り販売チャネルも自分たちで構築
海外に出るならローカライズが重要というお話をしましたが、最近の商品開発の流れが、ローカライズによって、どれも「モダンでシンプル」になりつつあって、それって面白くないなという思いがあったんです。一流の商品であれば、見せ方とか売り方の工夫をきちんとすることで、ローカライズしなくても受け容れられるのではないかと。
そこで、日本の伝統的な柄・サイズの和食器を6枚セットで箱膳に入れ販売する「OZENプロジェクト」をはじめました。
最初に、現地の富裕層の方に集まっていただいて、200枚ほどの和食器の柄をカードにしたもののなかから好きなものを10枚選んでもらい、その理由やどういう使い方をしたいか、いくらなら買うかといったことを、それぞれ10名ずつ、2~3時間インタビューしました。そして、その情報をもとにセレクトした6枚を箱膳に入れて販売したのですが、見る目のある方は「すごい」って買ってくれる。
これは、OZENプロジェクトに共感してくださったロンドンの富裕層の方がアンバサダー的な役割を果たしてくれて、知り合いの富裕層の方を集めてインタビューしてくださったから実現できたことです。今は隔月で、富裕層の方々をお呼びして、クローズドで和食のパーティーを開いています。シェフが「これはこういうお皿なので、この料理にしました」と、目の前で料理をお皿に盛りつけながら説明します。その場で召し上がっていただいて気に入ったら食器を買っていただく、直接販売のチャネルをつくっていきたいと考えています。

先日、ニューヨークの「CollectiveDesign」というアート&デザインフェアに出たんです。その時期のニューヨークは、町中でフェアが開催されていて、最高級のフェアだとピカソやダリなど美術館に並ぶような絵が置いてあるような世界です。2月に「ニューヨーク・ナウ」に出たときに、アートフェアの主催者の方から「数千万円クラスのものじゃなくて、気軽に買って帰れるような商品もほしいからぜひ出てくれないか」と声をかけていただいて参加しました。結果からいうと、高額の商品を多く販売することができました。会期前半はプレビューの日にVIPが直接、ブースに来て商品を見ていくんですけど、彼らは値段なんて見ない。後日、お抱えのインテリア・コンサルタントが来て「クライアントがこれに興味があると言っていたけど、これなら部屋に合うね。値段も問題ない」みたいな。富裕層が来るこんな展示会があるんだなと勉強になりました。

漠然と「富裕層に売りたい」と思っていても、富裕層のライフスタイルや好み、どんな金銭感覚かということを知らなければ、売れる商品はつくれません。
日本の商品は一般的に価格競争の面では不利です。富裕層をターゲットとするなら富裕層のペルソナ(顧客像)について1つの解答を持って商品開発を行い、自分たちでダイレクトに販売する方法も探っていかねばならないと思います。







